こんにちは(^^)/
『天神キュア矯正歯科』でございます☆彡
「以前よりも下あごが出てきたように感じる…」
「受け口かもしれないけど治したほうがいいのか自分のレベルがわからない」
このようなお悩みから、自分の口元に自信を持てない方はいませんか?
歯並びや歯の色など口元に関する悩みを抱える方は多くいますが、なかでも深刻なのがマスクで隠せない「あご」にまつわる悩みでしょう(。´・ω・)
あごの悩みはいくつかありますが、なかでも多い悩みが「受け口」です。
受け口は「反対咬合」「下顎前突」ともいわれており、下あごが上あごより前に出ている状態を指します。
受け口には種類やレベルがあるため自分が受け口かどうか、そして自分の受け口のレベルを判断するのは困難です(-_-;)
今回は、受け口についてわかりやすく解説していくと同時に受け口のレベルを判断する方法についても詳しく紹介していきます!
「自分は受け口かもしれない…」と受け口で悩まれている方は、ぜひ最後までお読みください(*’ω’*)
受け口ってどんな状態?
冒頭でも説明した通り、受け口は噛み合わせたときに、あごの位置が反対になる状態をいいます。
通常、噛み合わせたとき上の歯が下の歯を覆いますが受け口はその逆です。
受け口になると、わかりやすい特徴が顔の見た目でしょう。
下あごが発達するせいで顔が長く見え、「面長」の顔つきに近づきます( ;∀;)
また、サ行やタ行などが発音しにくいことや滑舌の悪さ、噛み合わせのバランスがおかしく咀嚼しにくいなどといった影響も出やすいでしょう。
しかし受け口といっても全員が同じ状態とは限りません。
人によって噛み合わせ具合や見た目の印象はさまざまです。
その理由は受け口の原因や種類、レベルにあります。
自分の受け口が、どの原因や種類に該当するか詳しくみていきましょう!
受け口の原因
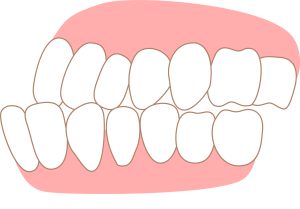
受け口の原因は、先天的要因と後天的要因の2種類に分けられます。
前者は親から子へ遺伝するケースで、後者は日常生活の癖が原因です。
受け口の原因①「先天的要因」
受け口のほとんどは遺伝による症例が多いといわれています。
あごの骨の形や位置関係、歯の大きさなど骨格的要因は遺伝からくる影響が大きいからです。
しかし両親が骨格的な問題を抱えていたとしても、かならずしも子へ遺伝するとは限りません。
受け口の原因②「後天的要因」
骨格的要因や歯の生え方に問題がなくても受け口になるケースが存在します。
それが日常生活の習慣からくる癖です。
乳幼児から指しゃぶりや口呼吸が習慣化すると、だんだん下の前歯が前方へ出てしまい受け口を引き起こしやすくなります。
大人になっても頬杖や猫背という癖から受け口になるケースもあるので注意しましょう。
3種類ある受け口の特徴

矯正歯科学的にみた受け口は、主に3種類に分類されます。
それぞれ、どのような特徴があるか自分の口元と照らし合わせてみてください。
受け口の種類①「歯槽性下顎前突」
歯槽性下顎前突は、あごの骨の大きさや位置関係が正常であるにもかかわらず受け口に見えてしまう特徴があります。
この場合、下の前歯の傾斜角度が大きく前方へ傾斜しているせいで受け口に見えてしまうのです。
日常生活の習慣によって引き起こされる症例が多く、矯正治療で歯並びを整えることで改善が期待できます。
受け口の種類②「機能性下顎前突」
機能性下顎前突は、歯の機能性や位置関係に問題があることで生じます。
噛み合わせたときに上下前歯が最初に当たり、奥歯まで噛もうとすると下あごが前方へ突出してしまう症状のことです。
前歯の切端同士が当たる「切端咬合」も機能性下顎前突に該当します。
受け口の種類③「骨格性下顎前突」
骨格性下顎前突は、名前の通り骨格異常が原因で起こる受け口であり、遺伝が特徴です。
一見、歯並びに問題がなくても下あごが出ているケースは骨格性下顎前突の可能性があります。
骨格異常とは、下あごの骨が過剰に成長したり上あごの成長が抑制されたりするなど上下の顎骨がアンバランスになっている状態です。
見た目からすぐに受け口だとわかるので、外見上コンプレックスを抱える方が多いといわれています。
自分が受け口か見分けるチェックポイント
ここまで受け口の原因や種類について触れましたが、自分の受け口がどれに当てはまるか確認できたと思います。
しかし、まだ自分が受け口かどうかわからない方もいるかもしれません。
自分が受け口かどうかを確認するためにチェックポイントを用意したので確認してみましょう。
もし該当する項目があれば、早めに歯科医院の受診をおすすめします(^o^)/

受け口かもしれないチェックポイント6つ
- 下の歯やあごが前方へ出ている
- 噛み合わせたとき上下の前歯がうまく噛めない
- 食事中にクチャクチャと音を立てている
- 麺類が噛み切れない
- サ行やタ行の発音が苦手または他人に滑舌を指摘される
- 家族に受け口の人がいる
自分の受け口レベルを確認しよう
ここから自分の受け口がどのレベルなのか症状別でみていきましょう。
レベルは軽度、中度、重度の3段階に分けられます。

軽度の受け口
軽度の受け口は骨格異常がなく若干下あごが前に出ている状態です。
歯並びが乱れていても外見上の影響が少なく、周囲も受け口かどうか気づきにくいでしょう。
日常生活を送るうえで大きな支障はないですが、やや発音しにくいという特徴があります。
中度の受け口
中度の受け口は下あごが上あごより前へ出ていることが容易にわかる状態です。
噛み合わせも上下の歯が正確に噛めず、滑舌や咀嚼に影響を及ぼします。
サ行やタ行の発音が苦手な方は中度の症状に当てはまるでしょう。
重度の受け口
重度の受け口は骨格的なバランスに問題があり、明らかに下あごが前へ突き出している状態が外見上からもわかります。
あごだけに限らず歯や顔の骨にも異常がある場合も多く、原因は遺伝が考えられるでしょう。
滑舌や発音、咀嚼にも影響が及びますが、それ以上に見た目の影響が強いといえます。
受け口を正確に診断する方法
受け口のレベルについて当てはまる項目はあったでしょうか?
もちろん書かれている症状以外にも当てはまる場合があるので、自己判断だけに頼らず歯科医院への受診をおすすめします!
歯科医院では、受け口の状態を知るために診断ツールをつかうため正確な診断が可能です。
レントゲン検査

レントゲン撮影は、歯の位置やあごの骨の状態がわかる検査法です。
平面からみる二次元診断や立体的映像が読み取れる三次元診断を基に、正確な診断をおこないます。
レントゲン撮影で受け口の原因やレベルの詳細が判断できるので、受け口の診断には欠かせない検査方法です(*’ω’*)
デジタル3Dスキャナー

デジタル3Dスキャナーは、口の中の状態を分析するために用いるツールです。
スティック状のカメラを口の中に入れ、光を当てながら歯の形や歯列データを3D上で素早く読みこみます。
読み取った情報はコンピューター上に記録として残り、分析や診断、治療計画に使用されます。
矯正治療のシミュレーションも可能であることから治療後のイメージがしやすい便利なアイテムです。
口腔内写真や顔貌写真の資料採り

矯正治療では、治療前の判断材料として口の中の写真と顔貌写真を撮影します。
歯の形や歯列の状態、顔の左右対称性、口を閉じたときの筋肉の緊張度合いなど、あらゆる角度から患者さまの情報を収集していくのです。
事前の資料があることで治療前後の比較や経過状況が明確になります。
受け口の治療法とは
診断ツールで状態を把握したあと、歯科医師が患者さまの状況に合わせて治療方針を決めていきます。
個人の状態によって治療法は異なりますが、軽度や中度であれば骨格的な問題が少ないことから矯正治療が中心となるでしょう。
しかし重度の場合は矯正治療だけでは難しいことから外科手術を視野に入れる必要があります。
受け口の治療①「マウスピース型矯正(インビザライン)」

マウスピース型矯正(インビザライン)は、透明なポリウレタン製のマウスピースを装着して矯正する治療法です。
1日20時間以上の装着が求められますが、取り外しができるため食事や歯磨きに支障がありません。
見た目からも周囲に矯正していることがバレにくく、金属アレルギーをもつ方でも安心して使用できる点がメリットです。
しかし適応する症例に限りがあるためマウスピース型矯正(インビザライン)を希望しても難しいと判断される場合もあります。
受け口の治療②「ワイヤー矯正」

従来の矯正治療といえばワイヤー矯正を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
ワイヤー矯正は、ブラケットやワイヤー装置を歯につけて移動させる矯正方法です。
取り外しがきかないことから食事や歯磨きがしにくい点がありますが、適応症例も多く細かい調整がしやすいというメリットがあります。
受け口の治療③「外科手術」

骨格に問題が生じている重度症例の場合は、外科手術を伴う可能性が高くなります。
早期治療が望ましく、子どもの場合は抜歯せずに上下のあごの大きさを揃えることが可能です。
大人になると下あごを削って後ろに下げる手術が適用される場合が多いでしょう。
本来、矯正治療は保険適用ではありませんが重度だと判断された場合、保険適用で手術が受けられます!
自分の受け口レベルが知りたいときは当院までお気軽にご相談ください

今回ご紹介した受け口のセルフチェックは、あくまでも簡単な確認方法です。
正しい診断方法とはいえないため、詳しい診断を希望される方は歯科医院の受診をおすすめします。
「歯科医院がこわい」
「こんなことで受診していいのかな?」
という患者さまのお声をよく耳にしますが、ご安心ください。
当院ではカウンセリングに力を入れており、患者さまの悩みや疑問に丁寧に向き合う姿勢を心がけています。
すこしでも悩まれている方は、まずは当院までお気軽にご相談してくださいね(^_-)-☆


