こんにちは😆
天神歯科・矯正歯科です🦷✨
本日は「顎が小さいと歯並びは悪くなる?」についてお話させて頂きます!
日本人(アジア人)は欧米人と比べると顎が小さいという特徴があります。
顎の大きさは歯並びに大きく関係してきます。
目次
顎の大きさと歯並び

日本人は欧米人と比べて顎のサイズは小さいですが、歯の本数は日本人も欧米人も同じです。
欧米人はキレイに歯が並べられても、日本人は顎が小さいので同じ本数の歯を綺麗に並べることは難しいです。
その為、歯並びがガタつきやすい傾向にあります😓
日本人全員が顎が小さいわけではありませんのでガタつきなどには差があります。
顎が小さい原因
日本人は顎が小さい特徴があるとお伝えしましたが、その原因は何なのか?🤔
遺伝
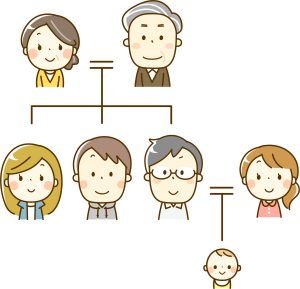
骨格は遺伝性が高く、顎の大きさも遺伝する可能性が高いです。
特に特徴的な骨格や大きさは遺伝する傾向があります。
食生活

顎の発育には食生活が大きく関わってきます。
飲み込みやすく食べやすいものや、軟らかいものばかりの食生活だと通常よりも噛む回数が少ないため顎の発達が鈍くなります。
顎の発育には筋肉をつけることが大事です。
その為には”しっかり食べ物を噛む”、”奥歯をきちんと使う”ということを心掛けて下さい。
噛む回数だけではなく、奥歯も使うことで横に動く力が加わり、顎の成長につながります!
しかし、顎や顔の成長は10歳頃までに80%程進んでおり、20歳頃で成長は止まると言われています。
ですので、こどもの頃からの食生活が重要になってきます。
顎が小さい特徴の歯並び
叢生

歯並びが前後に重なっていたり凸凹になっている状態です。
顎が小さいとひとつひとつの歯が綺麗に並ぶことが出来ず、スペースの取り合いになる為、歯並びが乱れる原因となります。
上顎前突(出っ歯)

上顎のアーチが欧米人に比べて、日本人(アジア人)は縦長で狭くなりやすいため、
上顎が前に出やすい傾向があります。
さらに下顎の成長不足によって、上顎に対して下顎が小さくなり、
下顎の前歯が通常よりも下がった位置になってしまうことから上顎前突(出っ歯)になってしまうケースも多いです。
顎が小さいことによる歯並びの改善
咀嚼筋を鍛える

日本人の顎が小さくなった原因のひとつとして、やわらかいものばかり食べるようになり、
食べ物を噛む機会が減り、顎の発達に影響が出てしまったということがあげられます。
食べ物をよく噛み、咀嚼筋を鍛えることで、歯並びのアーチを大きく出来る可能性があります。
しかし、あくまでも歯並びのアーチが大きくなる可能性があるだけで、顎が大きくなるわけではありません。
アーチが狭く凸凹だった歯並びが、アーチが広がることで正常な位置に歯が並んでくる為、歯並びの改善につながる可能性があるのです。
歯列矯正

咀嚼筋を鍛えて歯並びのアーチを広げ、歯並びが改善することもありますが、激的な改善は見込めません。
その為、大きな改善を望むのであれば歯列矯正をオススメ致します。
矯正装置を用いて歯列矯正を行うことによって、大きな歯並びの改善が可能です!
まとめ
日本人の顎の小ささは遺伝によるものや食生活によって顎の発達に影響が出てしまったことが主な原因とされています。
顎が小さいことで、歯並びに大きく影響し、生活に様々な影響を及ぼす為、歯並びの改善をオススメ致します。
歯並びが生活に及ぼす影響について今までのブログでもたくさんご紹介していますので、ぜひご覧ください!

